歯周治療における歯磨剤の効果についてーそのエビデンスとはー
歯周炎は口腔バイオフィルム中の細菌のディスバイオシスが関連した多因子疾患と考えられており、その本態は歯肉結合組織の炎症で、付着の喪失を引き起こし、進行すると歯の喪失を起こします。したがってその治療や予防には日々の口腔清掃が重要であり、歯面にプラークが付着しないように清潔することで歯肉の健康状態は維持されます。
日々のブラッシング時において、しばしば議論されるのが歯磨剤の効果です。歯磨剤の効果として期待されるのはまずフッ化物配合によるう蝕予防効果です。これについては十分なエビデンスがあり、特に歯周炎患者のように歯根が露出している場合には日々のブラッシングによるフッ化物の取り込みは必須ともいえます。これだけでも、ブラッシング時に歯磨剤を使うことの理由としては十分であると考えます。
もう一つは「抗菌効果」です。プラーク中の細菌はバイオフィルムという形で存在しているため、細菌が単体で存在している場合と比べて抗菌薬や消毒剤に500-1000倍抵抗力が高まっていると考えられます。したがって、口腔衛生の主体はあくまでも「機械的なプラークの除去」ですが、補助的に抗菌効果がある薬剤を配合することで、「機械的にバイオフィルムを破壊した上での薬効」を得ることは理にかなっている考えと思えます。
また、「抗炎症作用」をもつ薬剤を歯磨剤に配合することで、さらに歯肉の炎症を抑えるアプローチが考えられます。基本的にプラークさえ抑制されれば歯肉の炎症も起こりませんが、プラークスコアを完全にゼロにする事は難しく、ほとんどのヒトはどこかしらにプラークが残っています。そのような部位に補助的に抗炎症作用のある薬剤を到達させることで、予防効果が高まるかもしれません。このような抗菌効果と抗炎症効果をもつ成分としてフェノール化合物が考えられ、長期的な使用による歯周炎の進行を防ぐ効果があることがいくつかの研究で示されています。
今回はこれらの成分が配合された歯磨剤の効果についてエビデンスに基づいて解説していきたいと思います。
開催日: 2024年7月30日(火)
開催時間:19:30~20:15(日本時間)
講演者:日本歯科大学 生命歯学部歯周病学講座 准教授 関野 愉 先生
※講演後にQ&Aの時間を設けております。
※20:20~20:30は“Haleonヘルスパートナーからのお知らせ”です
視聴には事前登録が必要です。
その他のウェブ講演会情報
過去に開催したウェブ講演会ダイジェスト動画です。歯科医療従事者の日々の臨床をサポートする情報を提供しています。
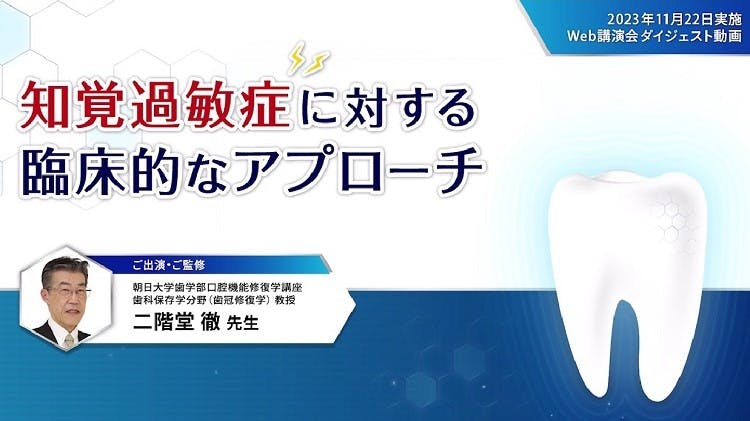
知覚過敏症に対する臨床的なアプローチ
2023年11月22日、「知覚過敏症に対する臨床的なアプローチ」と題して朝日大学歯学部口腔機能修復学講座 歯科保存学分野 歯冠修復学 教授 二階堂 徹 先生にご講演いただきました。この動画ではご講演内容の一部をご紹介いたします。

超音波スケーラーの望ましい使用法と最近の動向
2023年10月31日、「超音波スケーラーの望ましい使用法と最近の動向」と題して東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 総合診療歯科学分野 教授 新田 浩 先生にご講演いただきました。この動画ではご講演内容の一部をご紹介いたします。
この動画では、ご講演内容の一部をご紹介いたします。
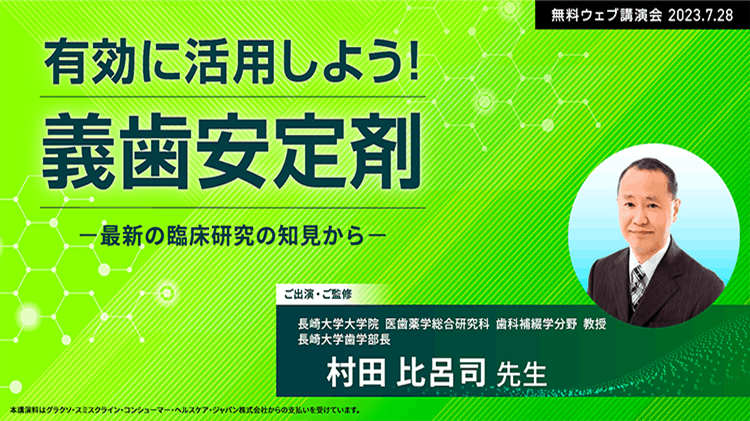
有効活用しよう!義歯安定剤 ―最新の臨床研究の知見からー
2023年7月28日、「有効活用しよう!義歯安定剤 ―最新の臨床研究の知見からー」と題して長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 歯科補綴学分野 教授 村田 比呂司先生にご講演いただきました。
この動画では、ご講演内容の一部をご紹介いたします。
